アメリカ
ライブドアブログ内の#アメリカタグが付いた新着記事や人気の記事をご紹介。
- このタグで
記事を書く
-

- being separated into new classes(クラス替え)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 変化新しい校舎に合わせて、クラス数が編成されたりなどの関係で、下期に入って、かなりクラスに変化があった。また、半年でカリキュラムが終了するクラスもあるので、新たに履修し直す生徒もいる。私も時間割は、変ったけど、あまり大きな変化は無い方かも。ESLクラスには、4人の新しい生徒が、加わった。ニカラグワから来たスペイン語を、話す姉弟2人と、韓国から来た韓国語を話す姉弟2人。ニカラグワの方は、殆ど英語力がなく、韓国の方は、ほどほどに、ある様だった。韓国人だけれど、アメリカに合わせた英語名を持っていて、Jan、Jafと言うファーストネームで、苗字がMooだそうだ。韓国も日本と同じ様に苗字を先にして、記名するそうで、Janが、辞書を使っているのを見たら、漢字で記名がされていた。韓国も漢字を使うとは知らなかった。数学は、上期と同じクラスだけど、私には、新しい席が与えられた。何人か、このクラスから脱落者が出たらしい。 けっこう難しいからね、このクラスは⋯。4限目にアダルトスクールに向かった。このクラスのメンバーだと、私は、ほとんど知った顔だった。ChrやMarやTinなど。上期には、ビギナークラスだったけど、今期は、ハイレベルクラス。大体が、チアリーダーのメンバーで、ダンスショウのためのダンスも凄くレベルが高い。 なんかいいなぁ。このクラスならば、もっとダンスを習える!多分、前回のダンスクラスのダンスショウにも参加するから、私は、5、6曲分のダンスに参加出来るはず! ラッキー!5限目のESLは、初めての履修したクラスなのに私は、全員の顔と名前を知っていた。今日は、色彩についてエッセイを書いた。6限目は、米歴史で、仲の良いAliとMarが、一緒だということが分かった。7限目の理科は、生徒が少し、1、2限目のクラスに流れたらしく、クラスメイトが減っていた。 17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/02/04 16:00
-

- go on a field trip(遠足に行く)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 遠足今日から新しいスケジュールで、下期が始まる。私は、明日からということになった。と言うのは、ESLクラスで、フィールドトリップとして、一日サンフランシスコに行くからだった。ESLの何人かの生徒は、参加する事なく学校に留まるらしい。イラン人のAli、タイ人のCin、メキシコ人のJohとFelとRigと私が、参加者だった。Mrs.Morは、3つ学校で先生をしている為、他に小学生と、中学生もこのフィールドトリップに参加していた。9:00a.m.頃に、スクールバスは、27人の生徒と3人の先生を乗せてサンフランシスコに向かった。1時間ほどで、目的地に着いた。着いた所は、港の倉庫だった。「あれ、美術館に行く予定じゃなかったの?」と思いながら引率者について行った。倉庫のドアの上には「MUSEUM」と書かれている。。。。。。あぁ、これは、再利用ってヤツですね。スライドを見て、お面を見て、絵を見て。壷を見て、人形を見て。。。。。。この Mexican Musium は、小規模な様子。でも、なかなか興味深い物が展示されていた。メキシコは、ネイティブアメリカンとスペイン人の文化で、大体が、出来上がっているのだと理解した。・・・・・・・・・・・・港湾11:00a.m.には、美術館から出ていた。この港の倉庫群は、本屋だったり、オフィスだったり、図書館だったり、劇場だったり、色々な種類の店で、楽しめそうだった。ピクニックエリアで、昼食をとり、食後の散歩で港を見た。あいにく、今日は、霧が出ていてゴールデンゲートブリッジを見る事は出来なかった。そのすぐ上の丘には、公園があった。沢山の人が、ランニングなどしていた。なかなか平和な公園だなぁ。ユースホステルがあるみたい。。。。。霧が出ていない天気の良さが揃えば、楽しめるエリアだと思った。17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/02/03 16:00
-

- 国連「助けて!アメリカに見捨てられたから運営費が尽きそうなの!」
- なんじぇいスタジアム@なんJまとめ
- 転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1770016188/1: それでも動く名無し 2026/02/02(月) 16:09:48.62 ID:k8T99hc+00202 国連が財政危機、米国の未払いが原因 運営費7月に枯渇の恐れ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN3107F0R30C26A1000000/ 【ニューヨーク=吉田圭織】国連のグテレス事務総長は29日までに加盟国向けの書簡で、通常予算の分担金の未払いによって財政危機が差し迫っていると警告した。日本経済新聞が入手した書簡によれば、状況が変わらなければ7月までに運営費が尽きる可能性が高いとも指摘した。名指しはしていないが、主因は米国の未払いとされる。 2: それでも動く名無し 2026/02/02(月) 16:16:47.36 ID:oRO7koj500202 もう解散でいいんじゃね
- 投稿日時:2026/02/02 17:27
-

- how to make a hamburger steak(ハンバーグの作り方)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 散髪テストが終わり、先生達が、生徒に成績をつけなくてはいけないので、今日は、生徒だけ休める日、Student out dayだった。まずは、大分、髪の毛が伸びて、特に、前髪がうっとうしくなったから、切ろう。ヘアーバンドで、髪の毛を留めて、チョキチョキ。目がサッパリした感じがする。けっこう目に、髪の毛が負担をかけていたんだなぁ。 N丘に行き、散髪で便利だったヘアバンドを探したけど、売られていなかった。・・・・・・・・・・・・手捏午後は、キャサリンに、バンクオブアメリカに降ろして貰い、送金を確かめた。 ついでに、1セントと25セントの束ロールを作ったので、それらを紙幣に替えてもらった。そのままダウンタウンからN丘に行き、すぐ傍の食料品店で卵を手に入れた。このお店は、玉子を普通の半額近い値で売ってるのだそうだ。そしてスーパーで、牛乳や玉葱やジャガ芋などを買った。さて、今夜の夕食を作るのは、私。冷蔵庫に、3、4日間、挽肉があったのが目に入っていた為、ハンバーグが食べたくなったから。ホフトファザーのBilが、たまに作るハンバーグは、肉だけで、他の具材は、何も入っていない、バンズで挟む為に作ってくれる。私は、玉葱入り、卵入り、牛乳入りのハンバーグが、食べたかった。そこで、消費期限が、ちょっと怪しくなっていた挽肉を使い、料理することにした。驚いたことに、M家の子供達は、この手のハンバーグを見たことがなかった様で、私が、肉とパン粉と卵と牛乳と玉葱を捏ねているのを見て、「Uh!yucky!」と言った。そりゃ、これは見た目はよくないけどね。。。。。。それで、いざ食べると、「もうないの?」と聞いてきた。でも、末っ子のAshは、相変わらず、見た目で判断し、彼女は、一口もハンバーグに手を出さなかった。日本では、ハンバーグとハンパーガーは、バンズの有る無しで、区分されているけど、アメリカは、どちらも「ハンバーガー」で、特に、呼び分けされていなかったのが、ちょっと変な感じ。しいて呼び分けするならば、バンス無しをハンバーグステーキと言うらしい。17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/02/02 16:00
-

- 【歴史が動いた】遂にアメリカで豚肉の〇〇が販売開始! 日本では当たり前だったのにマジで無かったアレ
- はちま起稿
- 投稿日時:2026/02/02 03:00
-
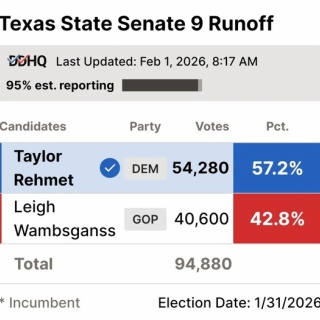
-

- 【アメリカ】CNN元司会者、移民摘発抗議デモをライブ配信して逮捕
- コノユビニュース
- 1 : 米連邦捜査当局は29日、中西部ミネソタ州の礼拝中の教会で起きた不法移民取り締まりへの抗議デモに関与したとして、著名ジャーナリストのドン・レモン氏を逮捕した。レモン氏はCNNテレビの元番組司会者で、教会でデモをライブ配信していた。米メディアが伝えた。 レモン氏はトランプ大統領に批判的な立場で知られる。レモン氏は、教会を訪れたのは取材のためで、デモ参加者とは無関係だと主張している。ほかにもジャーナリストら3人が逮捕された。 全文はソースで https://www.47news.jp/13799811.html
- 投稿日時:2026/02/01 18:09
-

- Keep your chin up.(上を向いて歩こう)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 手紙今日は、手紙書きで一日が、終わったと言っても良いほどだった。一月の初め頃に、私宛の手紙ラッシュがあったけど、その返事を書かなくてはいけなかった。あと、ずーっと、書こう書こうとしていたJoh宛の手紙もやっと書けた。彼女は、12月にあったパーティーで、知り合った私にクリスカードとクリスマスの切手を送って来てくれていた。あまりにも返事を書かなかったので、先方は、呆れたか、諦めていたかも?・・・・・・・・・・・・坂本ラジオをつけてたら、いきなり『上を向いて歩こう』が流れだした。洋楽を聴いていた時に、いきなり邦楽が流れたので驚いた。おぉ、坂本九さんだぁ。。。。。確か、飛行機事故で亡くなったよなぁ。それにしても、どうして、この曲が、全米で、一位になったのだろう?・・・・・・・・・・・・大工ここ最近、M家は、模様替えをしている。初めは、一階のTVルームにラッグが敷かれて、玄関のタイルが変わり、二階のバスルームが新しいマットと金色のバルブになり、ホストペアレントの寝室は、ベットカバーなど一新した。そして、今度は、一階のバスルームの洗面台が変わった。そして、今日は、二階の台所のマットが変った。その内キッチンの台は、タイル貼りにするそうだ。これらの仕事は、全部、ホストファザーのBilがやった。まぁ、一応は、大工さんらしいるからね。でも、本当は、彼は、エンジニアなんだそうだ。コンピューターをつくってた会社のスケジュールを組んだりするのが、彼の仕事だったそうである。近々、カーペットも新調するらしいし、ちょうど家の物が古くなったり、飽きて来た時期に私がホームステイしだしたタイミングだったみたい。M家が、ここに住みだして、今年で、四年目らしい。ホストシスターのKimは、この家を出て行ってしまったけど、もう一人のホストシスターのNeeは留まる様だい、M家は、人と動物が、本当、多い。今、犬が10匹もいる。ティンカーベルが、3匹の赤ちゃんを産んだし、無料で譲り受けたらしい更に、2匹の仔犬が来て、倍増した。17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/02/01 16:00
-
- ニューヨーク市で初のイスラム教徒の市長:ゾーラン・マムダニ市長は民主社会主義を唱えるが
- 刺激の強いことも発信するブログ
- アメリカ合衆国のニューヨーク市では今月、ゾーラン・マムダニ市長が初のイスラム教徒として市長に就任した。https://www.asahi.com/sp/articles/ASV111G57V11UHBI00BM.html市長としての宣誓式ではコーランに手を置いて宣誓。ウガンダにてインド系の家庭に生まれ、7歳の頃からニューヨーク市で過ごしてきた。https://www.asahi.com/sp/articles/ASV1223SRV12UHBI004M.html民主社会主義を強調する左派。積極財政ともいえる経済政策を強調。同時に。ムスリムを含む宗教や民族間での摩擦については何を思うのだろうか?https://www.asahi.com/sp/articles/ASV1X2VG7V1XUPQJ001M.html
- 投稿日時:2026/01/31 23:49
-

- Little House on the Prairie(大草原の小さな家)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 模様部屋を掃除しているうちに模様変えをしたくなりベッドを移動しだした。まぁ、次女のLinが、ベッドの下などにゴミを溜めていたこと。。。。。綺麗にしておく事に関して、おざなりなタイプの子なのだろうなぁ。・・・・・・・・・・・・公園午後の1時に、Linと自転車に乗って、すぐ近くのJM House に行った。州立の記念館になっている建物だ。JMさんは、ヨセミテ渓谷や セコイア国立公園 の保護に貢献した人で、けっこう有名人だったりする。その人が、M街に住んでいた家が、記念館になっていた。家屋は、なかなか、見応えがあって凄い!家具なども重厚で、高価そうなもので、家の最上部には、響きの良い鐘があり、"大草原の小さな家"に出てくる学校の鐘の音にそっくり。まぁ、開拓時代辺りに、生きた人になるのかな。こんな趣のある家に住めたら楽しい生活だろうなぁ。・・・・・・・・・・・・十柱夕食前にホストファザーのBilに送って貰い、ホストシスターのNeeと彼女の友達のWreと長男のJasと私とで、ボーリングに行った。そのボーリング場の施設が、古いこと、古いこと。スコアは、自分で書かねばならず、そんな経験は、初めて。いつも、ただボールを転がしていたので、ピンの数まで数えるなんて事するなんて面倒くさい。それに、今回は、調子が悪く、ガーターばっかり!Jasは、自分勝手な事ばかりするので、NeeやRenが「Katに言うわよ」とホストマザーに言い付ける事をほのめかしても言う事を聞きはしなかった。私はNeeに「今度ボーリングに来る時は、新しいボーリング場で、Jas無しでね」と言った。NeeのボーイフレンドのJasが、その場に居たら少しは楽しかったかもだけど、あいにく、彼は、彼の弟(2才)のベビーシッターをしているそうだ。Wreが「Akiのミドルネームは?」と聞いてきた。「私は、ミドルネームはないよ。大体の日本人は、ミドルネームを持たない」と答えた。彼女の名は、Wreというが、これは、鳥の名(ミソサザエ)で、一般的な名前ではない為、ミドルネームが要らず、彼女もミドルネームが無いそうだ。でも、彼女は、ミドルネームが欲しいらしく「大人になったら、ミドルネームを自分でつける」と言っていた。ちなみに彼女の苗字は、イギリスの地名だった。17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/01/31 16:00
-

- 国連、かなりマズい事になっていた・・・
- オレ的ゲーム速報@刃
- 投稿日時:2026/01/31 13:00
-

- アメリカに帰化し60年過ごしていた夫婦が手厚い社会保障を求めて日本に帰国し、帰化も検討→「タダ乗りだろ」と大炎上してしまう・・・
- オレ的ゲーム速報@刃
- 投稿日時:2026/01/31 11:30
-
- 2026年1月30日 HHS(米国保健福祉省)が連邦自閉症委員会を再編、反ワクチン派メンバーも参加(Cidrap)
- 新型コロナの「空気感染」について調べるブログ
- 2026年1月30日 HHSが連邦自閉症委員会を再編、反ワクチン派メンバーも参加(Cidrap) https://www.cidrap.umn.edu/childhood-vaccines/hhs-remakes-federal-autism-committee-includes-anti-vaccine-members 保健福祉省(HHS)は昨日、ロバート・F・ケネディ・ジュニア保健福祉長官に自閉症について助言する連邦委員会に21人の新メンバーが追加されたと発表した。 機関間自閉症調整委員会(IACC)の新しいメンバーには、医師、自閉症の当事者、自閉症児の親、自閉症支援団体に関係する人々が含まれます。 「トランプ大統領は、自閉症研究を21世紀に適応させるよう指示しました」とケネディ長官は保健福祉省のニュースリリースで述べた。 「私たちは、自閉症の研究、調査、そして治療において数十年の経験を持つ、最も有能な専門家、つまりリーダーを任命することで、この目標を実現しています。」
- 投稿日時:2026/01/31 11:23
-
- 2026年1月30日 研究によると、米国では低所得国よりもロングCOVID-19患者で脳の霧やうつ病の症状が一般的(Cidrap)
- 新型コロナの「空気感染」について調べるブログ
- 2026年1月30日 研究によると、米国では低所得国よりもロングCOVID-19患者で脳の霧やうつ病の症状が一般的(Cidrap) https://www.cidrap.umn.edu/covid-19/brain-fog-depression-more-common-long-covid-us-lower-income-countries-study-suggests ノースウェスタン大学のチームが主導し、今週「フロンティアズ・イン・ヒューマン・ニューロサイエンス」誌に発表された大規模分析によると、米国のロングCOVID患者は、低所得国の患者よりもブレインフォグやうつ病などの神経症状の発生率が著しく高いことが 報告されている。 米国では86%が脳の霧を報告、インドでは15%: 感染初期に入院しなかったロングCOVID患者(参加者の大半)のうち、米国では86%がブレインフォグを報告したのに対し、コロンビアでは62%、ナイジェリアでは63%、インドでは15%でした。不安や抑うつの症状は、米国の参加者の70%が報告したのに対し、コロンビアでは約68%、ナイジェリアとインドでは20%未満でした。 2026年1月28日ロングCOVID-19の神経学的症状に関する大陸間比較分析(フロンティアズ・イン・ヒューマン・ニューロサイエンス) https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2025.1760173/full ミレニア・ヒメネスミレニア・ヒメネス ら 目的: SARS-CoV-2(新型コロナ)感染症の急性期後遺症(Neuro-PASC)の神経学的症状を有する成人患者において、人口統計学的特性、併存疾患、神経症状、生活の質(QOL)、および認知機能転帰を比較すること。 結果: 合計3,157名が登録された(PNP 652名、NNP 2,505名)。 PNP患者は米国を除き圧倒的に男性が多かったのに対し、NNP患者はインドを除き圧倒的に女性が多かった。 最も頻度の高い神経症状は、ブレインフォッグ、筋肉痛、めまい、頭痛、感覚障害であり、米国で最も頻度が高く、インドで最も頻度が低かった。 PASCのほとんどの神経症状および非神経症状には有意差が認められ、これはPNP(入院後Neuro-PASC)コホートとNNPコホートの両方において、米国とコロンビアの患者で頻度が高かったことに起因する。 さらに、異なる機器で測定された認知機能障害は、PNP群とNNP群の両方において国によって異なっていた。多重対応分析の結果、症状負担は米国/コロンビアとナイジェリア/インドの間でクラスター化していることが示された。 結論: 神経性PASCは世界中で発生しているが、症状負担と心理的苦痛は地域によって異なり、これは社会文化的要因、医療アクセス、診断ツールの影響を受けている可能性が高い。 これらの知見は、世界中で文化に適応したスクリーニングとCOVID後のケアの必要性を浮き彫りにしている。
- 投稿日時:2026/01/31 11:21
-
-

- 【悲報】トランプ大統領「やっぱ韓国の関税25%にする、全部w」
- 稼げるまとめ速報
- 1: 稼げる名無しさん :2026/01/27(火) 10:01:23.06 ID:Xagk8VPp0 トランプ米大統領は26日(米東部時間)、韓国国会が両国間の関税合意履行に必要な法的手続きを進めていないと主張した上で、韓国への関税を合意以前の水準に引き上げると表明した。 この日SNSへの投稿で「韓国立法府が韓国と米国の合意を守らずにいる」とし、「これに伴い、自動車、木材、医薬品など、その他すべての相互関税を15%から25%に引き上げる」と明らかにした。 https://news.yahoo.co.jp/articles/0377ea6a3e565fdef2de3ef113e9d1210e808152 1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku対米投資を渋ったためとのこと。 これはマズイとのことで、大慌てで訪米みたいだな。ソース:韓国の通商当局トップら急きょ訪米 「トランプ関税」阻止へ総力戦
- 投稿日時:2026/01/30 22:00
-
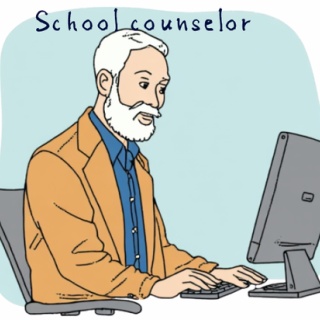
- Say it sharply(ピシャリと言う)
- M家の人々と《アメリカ高校留学日記》
- 痛烈ESLのテスト中だったけど、カウンセラーのMr.Hovの予約がとれたので、一階の彼のオフィスに向かった。「5限目のMrs.MayのESLを履修したいのだけれど⋯⋯⋯⋯」と私は言った。彼は「ちょっと待って 」と言ってパソコンのキーボードをたたいて、今の私のスケジュールをコンピューターの画面に出した。そして、まず、5限目のダンスクラスをESLへと打ち込んで変えた。次にダンスクラスを本当は1限目のESLと交換しようと私は、思っていた。だけれどもダンスクラスの先生、Mrs.Barは、今まで持っていた1限目と2限目の授業を止めて、保健の授業を手伝う事にするらしい。と言うことは、どこにダンスクラスを入れるか。。。。。。残りの3、4限目のどちらかにダンスクラスを入れないといけなくなる。4限目に入れると、今迄、4限目にあった米歴史は、6限目に移した。では、ドラマクラスは?そこで、私は、「ESLをひとつ落とすことは出来ないか?」と私は言った。すると、Mr.Hovは「君の英語力は、良くない。もっと、ESLをとるべきだ」とピシャリと言って来た。えぇぇぇ!?「全部とることは、出来ないよ。ドラマクラスかダンスクラスを諦めなくちゃね」と彼は言う。うーん、こんな話の流れになるとは思わなかったなぁ。どちらをとるかとなると、絶対にダンスクラスだよなぁ、やっぱり。だいたい発表会に向けてもう練習に入ってもいる事だしね。新しいスケジュールは、火曜日、1月29日から始まるそうだ。この日は、ESLのフィールドトリップでMrs.Mor達とサンフランシスコに行くから、私にとっては、1月30日からスタートということになる。・・・・・・・・・・・・彼氏ホストファミリーの次女のLinに10本の棒付きキャンディーを売って貰う様に渡しておいたけど、その内の3本を長男のJasに盗られたと彼女が言った。彼にに「3本のロリポップは?」と聞くと「知らないよ。Linが無くしたんだ」と言う。どうしたら良いかとホストマザーのKatに言ってみた。Katは「私は、Linを信じる。多分、Jasが盗ったのよ。よくそういう事をする子だから」と私に3本分のロリボップ代の1ドル50セントを渡してくれた。彼は、自分をコントロールする事が出来ないのだそうだ。それにウソをつくことに対しても何も感じないのだそうだ。「特別学校の先生と一緒に、私達は彼を治す様に、今、努力しているのよ」とKatは言った。 17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。高田 ふーみんダイヤモンド社2025-03-05
- 投稿日時:2026/01/30 16:00
-
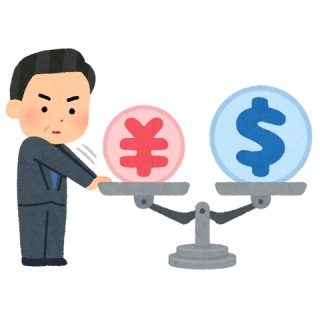
- 米財務省、日本を引き続き「監視対象」に指定 “為替操作”調査報告書を公表
- 稼げるまとめ速報
- 1: 稼げる名無しさん :2026/01/30(金) 10:30:30.78 ID:EM71FT7+9 ※1/30(金) 7:38 日テレNEWS NNN アメリカの財務省は29日、各国が通貨を安く誘導する為替操作を行っていないかを調査した報告書を公表し、日本を引き続き「監視対象」に指定しました。 米財務省、日本を引き続き「監視対象」に指定 “為替操作”調査報告書を公表 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/ntv_news24/world/ntv_news24-2026013002726218 1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku日本側としては「そんな無茶な...」といったところ。今朝発表の東京都区CPIも対前年同月比+2.0%まで鈍化していたわけで。 米国もここから大きくは利下げできなさそうだしな。やる夫より:本日金価格に強めの調整(下落方向)が入っているお [H Holy] 純金 24金 24K ウィーン金貨ペンダントトップ 造幣局刻印入り 価格: 90800円 (2026年01月30日調査価格) ポイント: 1,816 (2%)pt キャンペーン: 2/2 23:59まで 10,000円以上お買い物等の条件達成でポイントアップ (諸条件あり) 細則を確認 Amazonで見る Powered by 稼げるまとめ速報 [H Holy] 純金 24金 24K ウィーン金貨ペンダントトップ 造幣局刻印入り の詳細はこちら
- 投稿日時:2026/01/30 12:40
-
- 2026年1月30日 米国人平均寿命、24年は過去最長79歳 コロナや薬物要因が急減(ロイター)
- 新型コロナの「空気感染」について調べるブログ
- 2026年1月30日 米国人平均寿命、24年は過去最長79歳 コロナや薬物要因が急減(ロイター) https://news.yahoo.co.jp/articles/7893880226b7df0f09f2fc2b2e2150abd470b58c 米疾病対策センター(CDC)は29日、2024年の米国人の平均寿命が前年比6カ月長くなり、過去最長の79歳となったと発表した。新型コロナウイルス感染症と薬物の過剰摂取による死者が急減したことが要因だった。 2026年1月30日 米国人平均寿命、24年は過去最長79歳 コロナや薬物要因が急減(ロイター) https://news.yahoo.co.jp/articles/7eabd4fabdcb4fbad5449deb20c8f62b4e34a8c8 米疾病対策センター(CDC)は29日、2024年の米国人の平均寿命が前年比6カ月長くなり、過去最長の79歳となったと発表した。新型コロナウイルス感染症と薬物の過剰摂取による死者が急減したことが要因だった。 2026年1月 2024年の米国の死亡率(CDC) https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db548.htm ・米国人口の平均寿命は2024年に79.0歳となり、2023年より0.6歳増加した。 ・年齢調整死亡率は、2023年の米国標準人口10万人あたり750.5人から2024年には722.1人に3.8%減少した。 ・年齢別死亡率は、5~14歳を除く1歳以上のすべての年齢層で2023年から2024年にかけて減少しました。 ・自殺はCOVID-19に代わって第10位の死因となり、心臓病、がん、不慮の事故は2024年も引き続き上位3位を占めた。 ・乳児死亡率は、2023年(出生10万人あたり乳児死亡数560.2人)から2024年(552.5人)にかけて大きな変化はなかった。
- 投稿日時:2026/01/30 11:23
-